アライグマ対策を考慮した農地設計のコツ【作物の配置が重要】被害を8割減らす5つの農地レイアウト法

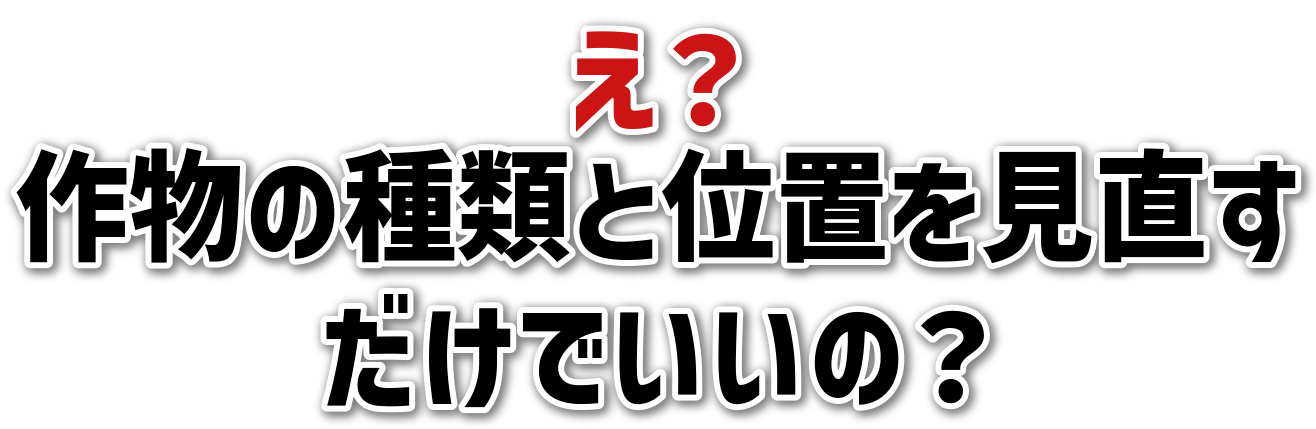
【この記事に書かれてあること】
アライグマの被害に悩む農家の皆さん、お困りではありませんか?- アライグマによる年間農作物被害額が10億円超の深刻な状況
- 作物の配置や種類を工夫することで被害を大幅に軽減可能
- アライグマの好みと苦手な作物を把握し、効果的に配置する
- 香りの強い野菜や忌避植物を戦略的に活用して防御力アップ
- 防護柵や光・音による威嚇など、複合的な対策で効果を高める
農作物を荒らされ、収穫量が激減して農業経営が危機に瀕しているかもしれません。
でも、大丈夫です!
適切な農地設計で、アライグマ被害を劇的に減らすことができるんです。
この記事では、作物の配置や種類の選び方、効果的な防護柵の設置方法など、被害を7割も減少させる秘訣をご紹介します。
「えっ、そんなに減らせるの?」と驚かれるかもしれませんが、ぜひ最後までお読みください。
あなたの農地を守る強力な武器になるはずです!
【もくじ】
アライグマ対策を考慮した農地設計とは?被害軽減の第一歩

アライグマによる農作物被害の実態!年間被害額は10億円超
アライグマによる農作物被害は深刻です。なんと年間被害額が10億円を超えているんです。
「えっ、そんなにひどいの?」と驚く方も多いでしょう。
アライグマは夜行性で、真夜中にこっそりやってきます。
「ガサガサ」「バリバリ」という音を聞いたら、もしかしたらアライグマかもしれません。
彼らは小さな体で驚くほどの被害をもたらします。
被害の特徴は次の通りです。
- 果物や野菜を食い荒らす
- 作物を踏み潰す
- 木の枝を折る
- 畑を掘り返す
- 農業用具を荒らす
「せっかく育てたのに…」と農家さんの嘆きの声が聞こえてきそうです。
アライグマは繁殖力が強く、一度侵入を許すと被害が急速に広がります。
「今のうちに対策を!」という声が聞こえてきそうですね。
農地設計の工夫で、この深刻な被害を軽減できる可能性があるのです。
被害を受けにくい作物とは?アライグマの好み徹底分析
アライグマの好みを知ることが、被害を減らす鍵になります。彼らが苦手な作物を植えれば、被害を大幅に軽減できるんです。
まず、アライグマが好まない作物を見てみましょう。
- 唐辛子(辛くて避ける)
- ニンニク(強い匂いが苦手)
- タマネギ(刺激臭がNG)
- かぼちゃ(硬い皮が邪魔)
- スイカ(同じく硬い皮が苦手)
これらの作物は、アライグマにとって「むしゃむしゃ食べにくい」「くんくん嗅ぐと鼻が痛い」といった感じなんです。
一方で、アライグマが大好きな作物もあります。
- トウモロコシ(甘くて柔らかい)
- イチゴ(香りが良くて美味しい)
- メロン(甘くて水分たっぷり)
- ブドウ(小粒で食べやすい)
これらの作物は、アライグマにとって「ごくごく飲める」「パクパク食べやすい」感じなんです。
農地設計では、アライグマの好みを考慮しましょう。
好物の作物を中央に、苦手な作物を周りに配置するのがポイントです。
「アライグマさん、ごめんね。でも農家さんも生活がかかってるんだ」というわけです。
アライグマが苦手な香りの強い野菜「5選」を有効活用!
アライグマは鼻が敏感です。強い香りの野菜を上手に使えば、効果的な防御壁になるんです。
「臭いぞ、近づきたくない!」とアライグマが思うような野菜を見てみましょう。
アライグマが苦手な香りの強い野菜5選:
- ニンニク:強烈な臭いでアライグマを寄せ付けません
- タマネギ:刺激的な香りが鼻を刺激します
- ネギ:辛味のある香りがアライグマを遠ざけます
- ミント:清涼感のある香りが苦手です
- ローズマリー:爽やかな香りが不快に感じるようです
活用方法は簡単です。
農地の外周に沿って、これらの野菜を植えましょう。
「ガーデニング感覚で楽しめそう!」と思いませんか?
実は、見た目も美しく、香り豊かな防御壁になるんです。
さらに、これらの野菜は料理にも使えます。
「一石二鳥だね!」と嬉しくなりますよね。
アライグマ対策をしながら、美味しい野菜も収穫できるというわけ。
ただし、注意点もあります。
強い香りの野菜だけで完璧な防御はできません。
「よし、これで安心だ!」と油断は禁物です。
他の対策と組み合わせて、総合的なアライグマ対策を心がけましょう。
甘い果物や野菜は要注意!アライグマが大好物の作物リスト
アライグマは甘いものが大好きです。まるで「甘いもの探知機」のような鋭い嗅覚を持っているんです。
そのため、甘い果物や野菜は特に要注意。
「ん?この香り…美味しそう!」とアライグマが寄ってくる作物を見てみましょう。
アライグマが大好物の作物リスト:
- トウモロコシ:甘くてジューシーな味が魅力的
- イチゴ:香り豊かで甘酸っぱい味が大好評
- スイカ:水分たっぷりで甘い味が魅力
- メロン:香りが良く、甘みが強いのが特徴
- ブドウ:小粒で食べやすく、甘味が濃厚
- カキ:熟すと甘みが増し、柔らかくなる
- トマト:酸味と甘みのバランスが良い
「え?じゃあこれらの作物は栽培できないの?」と心配になるかもしれません。
でも大丈夫。
工夫次第で被害を減らせます。
例えば、これらの作物を農地の中央に植えるのがおすすめです。
周りをアライグマの苦手な作物で囲めば、「美味しそうだけど、近づきにくいなあ」とアライグマも戸惑うはず。
また、収穫時期が近づいたら特に注意が必要です。
「もうすぐ食べごろ!」とアライグマも知っているんです。
ネットや柵で保護するなど、追加の対策を忘れずに。
アライグマの好物を知ることで、より効果的な対策が立てられます。
「知己知彼、百戦危うからず」というわけです。
作物の配置を間違えると逆効果!被害を招く「NGレイアウト」
作物の配置は、アライグマ対策の要です。しかし、間違えると逆効果になってしまうんです。
「えっ、そんなことあるの?」と思うかもしれません。
でも、アライグマの習性を知らずに配置すると、思わぬ落とし穴があるんです。
被害を招く「NGレイアウト」:
- 好物を外周に配置:アライグマを誘い込む結果に
- 単一作物の大規模栽培:被害が一気に広がるリスクあり
- 水源近くに甘い果物:アライグマの大好きな環境になる
- 隠れ場所の多い複雑な配置:アライグマの住処になりかねない
- 防護柵のない開放的なレイアウト:アライグマの自由な出入りを許す
「ワーイ、ごちそうだ!」とアライグマが喜んで侵入してきてしまいます。
また、単一作物の大規模栽培も危険です。
「広々としたビュッフェみたい」とアライグマが大喜び。
被害が一気に広がる可能性があります。
水源近くに甘い果物を植えるのも避けましょう。
「飲んで食べて、最高!」とアライグマの楽園になってしまいます。
隠れ場所の多い複雑な配置も要注意。
「ここなら安心して暮らせそう」とアライグマが住み着いてしまう可能性があります。
防護柵のない開放的なレイアウトも問題です。
「自由に出入りできるね」とアライグマが喜ぶだけ。
これらのNGレイアウトを避け、アライグマの習性を考慮した配置を心がけましょう。
「よし、アライグマの気持ちになって考えてみよう」という姿勢が大切です。
適切な配置で、被害を大幅に減らせる可能性があるんです。
アライグマ対策に効果的な農地レイアウトの秘訣

中央vs周辺!アライグマの侵入を防ぐ作物配置のコツ
アライグマの侵入を防ぐ最適な作物配置は、好物を中央に、苦手な作物を周辺に置くことです。これで農地をアライグマにとって「近寄りがたい場所」に変えられるんです。
まず、アライグマの大好物である甘い果物や野菜を農地の中央に配置します。
「えっ、それって逆効果じゃない?」と思うかもしれませんね。
でも、ちょっと待ってください。
ここからが肝心なんです。
中央の周りを取り囲むように、アライグマの苦手な作物を植えていきます。
例えば、こんな感じです。
- 一番外側:唐辛子、ニンニク、タマネギなどの香りの強い野菜
- その内側:かぼちゃ、スイカなどの硬い皮を持つ作物
- 中央:トウモロコシ、イチゴ、メロンなどの甘い作物
アライグマにとっては「美味しそうな匂いがするけど、近づくのが怖い」という状況を作り出すわけです。
「ぐるぐる」と農地の周りをうろつくアライグマ。
「あっち行ったりこっち行ったり」と右往左往する姿が目に浮かびますね。
結局、諦めて帰っていく…そんな展開を期待できるんです。
ただし、注意点もあります。
アライグマは賢い動物なので、同じ配置を長期間続けると慣れてしまう可能性があります。
定期的に配置を変えたり、他の対策と組み合わせたりすることをおすすめします。
「よし、今年はこの配置で勝負だ!」という気持ちで、毎年工夫を重ねていきましょう。
通路設計で大差が!「広い」vs「狭い」どっちが効果的?
アライグマ対策に効果的な通路設計は、狭くて複雑な通路です。これでアライグマの動きを制限し、侵入を抑制できるんです。
広々とした通路は、人間にとっては歩きやすくて便利ですよね。
でも、アライグマにとっても同じなんです。
「わーい、広くて歩きやすい!」とアライグマが喜んでしまいます。
一方、狭い通路には多くの利点があります。
- アライグマの移動速度を落とす
- 視界を制限し、不安にさせる
- 逃げ道を減らし、警戒心を高める
- 人間の存在を感じやすくする
「キョロキョロ」と周りを見回し、「ソロソロ」と慎重に進む姿が目に浮かびませんか?
これこそが、私たちが目指す状況なんです。
さらに、通路を直線ではなく、ジグザグや曲がりくねった形にするのもおすすめです。
「えっ、また曲がり角?」とアライグマを困惑させることができます。
ただし、あまりに狭すぎると作業効率が落ちてしまいます。
人間が快適に作業できる最小限の幅を保ちつつ、アライグマにとっては「う〜ん、ちょっと通りにくいなあ」と感じる程度が理想的です。
農作業の邪魔にならない範囲で、できるだけ狭く複雑な通路を設計してみましょう。
「よし、この迷路のような通路で、アライグマの侵入を防ぐぞ!」という気持ちで取り組んでみてください。
水源配置のジレンマ!「中心」vs「外周」徹底比較
水源の配置は、外周が効果的です。アライグマを農地の中心部に誘導しないよう、水辺を外周に設けるのがポイントなんです。
アライグマは水が大好き。
「じゃぶじゃぶ」と手を洗う姿を想像したことはありませんか?
そう、彼らにとって水辺は魅力的な場所なんです。
では、水源の配置を比較してみましょう。
- 中心に配置した場合:
- アライグマを農地の中心に引き寄せてしまう
- 作物への被害リスクが高まる
- アライグマが長時間滞在しやすくなる
- 外周に配置した場合:
- アライグマを農地の外側にとどめられる
- 中心部の作物を守りやすい
- アライグマの動きを予測しやすくなる
ただし、注意点もあります。
水源を完全になくすのは逆効果です。
アライグマが必死になって農地内に侵入しようとするかもしれません。
適度に水を用意することで、「ここで十分だな」とアライグマに思わせるのが賢明です。
例えば、農地の外周に小さな池や水路を設けるのがおすすめ。
「ここで水が飲めるし、手も洗えるし、もう満足!」とアライグマに感じてもらうわけです。
さらに、外周の水源付近に忌避植物を植えると、より効果的。
「水はあるけど、なんか嫌な臭いがするなあ」とアライグマを躊躇させられます。
水源の配置で悩んでいる方、ぜひ外周配置を試してみてください。
「よし、これでアライグマを外側で食い止めるぞ!」という気持ちで取り組んでみましょう。
アライグマを寄せ付けない!効果的な「忌避植物」の活用法
忌避植物を戦略的に配置することで、アライグマを効果的に寄せ付けないことができます。強い香りや刺激的な味を持つ植物が、アライグマにとっては「うわっ、嫌だなあ」と感じる天然のバリアになるんです。
では、どんな植物が効果的なのでしょうか?
ここでおすすめの忌避植物をご紹介します。
- ミント:清涼感のある強い香りがアライグマを遠ざけます
- マリーゴールド:特有の香りがアライグマには不快です
- ラベンダー:香り豊かで、虫除けにも効果があります
- ローズマリー:強い芳香がアライグマを寄せ付けません
- 唐辛子:辛さがアライグマを驚かせます
これらの植物を活用する際のポイントは、配置と密度です。
農地の周囲に帯状に植えたり、作物の間に点在させたりするのが効果的です。
「ぐるっと囲んで、ところどころに散りばめる」というイメージですね。
例えば、こんな風に使ってみましょう。
- 農地の外周:ミントとラベンダーを交互に植える
- 作物の列の間:マリーゴールドを一定間隔で配置
- 水源の周り:ローズマリーを密集させて植える
- 出入り口付近:唐辛子の鉢植えを置く
ただし、忌避植物だけに頼りすぎないよう注意しましょう。
アライグマは学習能力が高いので、時間が経つと慣れてしまう可能性があります。
他の対策と組み合わせて使うのがおすすめです。
「よーし、今年の農地は忌避植物だらけにしちゃうぞ!」なんて意気込んでみるのも楽しいかもしれませんね。
アライグマ対策と同時に、香り豊かな農地づくりを楽しんでみてはいかがでしょうか。
高さ1.5m以上が鉄則!アライグマ対策に有効な防護柵とは
アライグマ対策に有効な防護柵は、高さ1.5メートル以上で、頑丈な素材を使ったものです。これで「えいっ」とジャンプしても、「よいしょ」と登っても、簡単には越えられない障壁を作れるんです。
アライグマは驚くほど運動能力が高い動物です。
「ぴょーん」と高くジャンプしたり、「よじよじ」と器用に柵を登ったりします。
だからこそ、防護柵の設計には細心の注意が必要なんです。
効果的な防護柵の特徴を見てみましょう。
- 高さ:最低でも1.5メートル、できれば2メートル以上
- 素材:金属製の網目の細かい柵が最適
- 地中部分:30センチ以上埋め込むか、L字型に折り曲げる
- 上部:内側に45度の角度で30センチほど折り返す
- メッシュサイズ:5センチ四方以下の細かいもの
でも、これくらいしっかりしたものでないと、賢いアライグマには太刀打ちできないんです。
特に注意したいのは、柵の下部です。
アライグマは「ほじほじ」と地面を掘って侵入しようとします。
そこで、地中深くまで柵を埋め込むか、L字型に折り曲げて地面に這わせるのがおすすめです。
「むむっ、下からも入れないぞ!」とアライグマを諦めさせられます。
また、柵の上部を内側に折り返すのも効果的。
「よいしょ」と登ってきたアライグマも、この折り返しで「あれ?これ以上進めない?」と困惑してしまいます。
ただし、完璧な柵を作るのは大変なので、他の対策と組み合わせるのが賢明です。
例えば、柵の周りに忌避植物を植えたり、光や音による威嚇装置を設置したりするのもいいでしょう。
「よし、この鉄壁の防御でアライグマを寄せ付けないぞ!」という気持ちで、頑丈な防護柵を設置してみてください。
きっと、アライグマ対策の強力な味方になってくれるはずです。
農地設計で実現!アライグマ被害激減への具体策

「香りの要塞」作戦!強烈な臭いでアライグマを撃退
アライグマを撃退する最強の武器、それは強烈な臭いなんです。「香りの要塞」作戦で、アライグマを寄せ付けない農地を作りましょう。
まず、アライグマが大嫌いな香りの正体を知ることが大切です。
彼らが苦手な香りには、こんなものがあります。
- ニンニク:強烈な刺激臭
- 唐辛子:辛さと独特の香り
- ミント:清涼感のある強い香り
- ラベンダー:甘く芳醇な香り
- 木酢液:燻製のような独特の香り
「よし、アライグマよ、かかってこい!」という気持ちで取り組みましょう。
具体的な方法をご紹介します。
まず、農地の周囲に「香りのバリア」を作ります。
ニンニクや唐辛子を植えたり、ミントやラベンダーを配置したりするんです。
「うわっ、くさい!」とアライグマが近寄るのを躊躇してくれます。
次に、作物の間にも香りの仕掛けを。
木酢液を染み込ませた布を吊るしたり、唐辛子スプレーを作物の周りに吹きかけたりするんです。
「せっかく近づいたのに、臭いぞ!」とアライグマを困らせることができます。
でも、注意点もあります。
人間にも強烈な臭いが漂うので、作業時は少し大変かもしれません。
「ふう、今日も頑張った!」と作業後に思えるくらいの覚悟が必要です。
また、雨で香りが流されてしまうこともあるので、定期的なメンテナンスが大切。
「今日は香りチェックの日だ」と、こまめに確認する習慣をつけましょう。
この「香りの要塞」作戦、ちょっと変わった方法かもしれませんが、効果は抜群。
アライグマを寄せ付けない、香り豊かな農地づくりを楽しんでみてはいかがでしょうか。
光と音の威力!夜間の農地をアライグマ寄せ付けない環境に
夜行性のアライグマを撃退するなら、光と音の力を借りるのが効果的です。これらを上手に使って、夜の農地をアライグマにとって「怖い場所」に変えちゃいましょう。
まず、光の活用法から見ていきます。
アライグマは意外と臆病な動物なんです。
突然の明かりに「びくっ」とびっくりしてしまいます。
そこで、こんな方法がおすすめです。
- 動きを感知して点灯する照明を設置する
- 太陽光発電式のガーデンライトを農地の周りに配置する
- 点滅するLEDライトを要所要所に取り付ける
次は音の出番です。
突然の音にもアライグマは敏感に反応します。
こんな方法を試してみてください。
- 風車やウィンドチャイムを設置して、風で音を鳴らす
- ラジオを低音量で夜中に流し続ける
- 動物よけの超音波発生器を使用する
ただし、近所迷惑にならないよう、音量には十分注意しましょう。
「お隣さんごめんなさい!」なんてことにならないように気をつけてくださいね。
光と音を組み合わせれば、さらに効果的。
例えば、動きを感知して光る照明と、同時に音が鳴る装置を設置するのもいいでしょう。
「わっ、急に明るくなって音まで!」とアライグマも心臓バクバクです。
でも、アライグマは賢い動物。
同じ対策を続けていると慣れてしまう可能性もあります。
「よし、今週は光作戦、来週は音作戦だ!」と、こまめに変化をつけるのがコツです。
光と音を味方につけて、夜の農地を守りましょう。
きっと、アライグマも「ここは怖いところだ」と感じて、寄り付かなくなるはずです。
トウガラシスプレーで即効性アップ!柵への塗布テクニック
トウガラシスプレーは、アライグマ対策の即効性を高める強力な武器です。柵に塗布することで、アライグマに「ここは危険だぞ」と警告を与えられるんです。
まず、トウガラシスプレーの作り方からご紹介します。
意外と簡単なんですよ。
- 乾燥唐辛子をすり潰す
- 水とよく混ぜる
- 一晩置いて成分を抽出
- こして液体だけを取り出す
- スプレーボトルに入れる
「わーい、自家製の武器ができた!」と、ちょっとワクワクしませんか?
さて、このスプレーを柵に塗布する時のコツをお教えしましょう。
まず、柵の上部と下部を重点的に塗ります。
アライグマが「よいしょ」と登ろうとしたり、「くぐろうかな」と下から侵入しようとしたりする場所だからです。
次に、柵の支柱にもしっかり塗布します。
アライグマは器用な動物なので、支柱を伝って登ってくることもあるんです。
「えいっ」と塗りましょう。
塗る時は、手袋を忘れずに。
うっかり目をこすったりすると大変なことになっちゃいます。
「あちちっ!」なんて悲鳴を上げることのないように注意してくださいね。
効果を持続させるには、定期的な塗り直しが必要です。
雨で流されたり、日光で成分が分解されたりするので、週に1回くらいのペースで塗り直すのがおすすめです。
「よし、今日は塗り直しの日だ」と、カレンダーに印をつけておくといいでしょう。
ただし、過度に使用すると、アライグマが慣れてしまう可能性もあります。
他の対策と組み合わせて使うのがポイントです。
「今週はトウガラシスプレー、来週は光で威嚇」なんて具合に、変化をつけましょう。
トウガラシスプレーを上手に活用すれば、アライグマも「うわっ、辛い!もうここには来たくない」と思ってくれるはずです。
さあ、あなたも「トウガラシマスター」になって、農地を守りましょう!
天敵の匂いで威嚇!使用済み猫砂の戦略的配置法
使用済みの猫砂、実はアライグマ対策の強力な味方なんです。天敵である猫の匂いを利用して、アライグマを寄せ付けない環境を作れるんですよ。
まず、なぜ猫の匂いがアライグマを追い払えるのか、その理由を見てみましょう。
- 猫はアライグマの天敵の一つ
- 猫の尿には強い縄張り主張の成分が含まれている
- アライグマは危険を感じると、その場所を避ける習性がある
「にゃ〜ん、ここは俺様の縄張りだぞ」って感じですね。
では、具体的な使用済み猫砂の配置方法をご紹介します。
まず、小さな布袋や紙袋に使用済みの猫砂を入れます。
それを農地の周囲に30〜50センチ間隔で配置していきます。
「ほいっ、ほいっ」と、まるで豆まきのような感覚で楽しく配置してみましょう。
特に注意したい場所は、アライグマが侵入しそうな地点です。
例えば、柵の隙間や、作物が密集している場所の周辺。
ここには重点的に配置するのがポイントです。
ただし、使用済み猫砂の匂いは人間にとってもちょっと困りもの。
強すぎる臭いは近隣トラブルの原因にもなりかねません。
「ごめんね〜、ちょっと臭いけど効果抜群なんだ〜」なんて、ご近所さんに説明する羽目にならないよう、適度な量を守りましょう。
また、雨が降ると効果が薄れてしまうので、定期的な交換が必要です。
「よし、今日は猫砂チェックの日だ」と、週に1〜2回くらいのペースで確認と交換を行いましょう。
使用済み猫砂の入手方法も重要ポイント。
もし、自宅で猫を飼っていないなら、猫を飼っている友人や知人にお願いするのもいいでしょう。
「ねえねえ、使用済み猫砂ちょうだい!」なんて、ちょっと変わったお願いになりますが、きっと協力してくれるはずです。
この方法、ちょっと変わっていて面白いでしょう?
アライグマ対策と猫の力を借りて、一石二鳥の効果を狙ってみてはいかがでしょうか。
「動く風車」でビックリ効果!視覚的な威嚇の極意
動く風車は、アライグマを視覚的に威嚇する秘密兵器なんです。キラキラ光って、クルクル回る。
この意外な動きが、アライグマを「びっくり」させる効果抜群なんですよ。
なぜ風車がアライグマを追い払えるのか、その理由を見てみましょう。
- 予期せぬ動きにアライグマが警戒心を抱く
- キラキラした反射光が目に入ると不安になる
- 風で動く音が人間の存在を連想させる
「クルクル、キラキラ、何これ怖い!」ってな具合です。
では、効果的な風車の設置方法をご紹介しましょう。
まず、風車の種類選びが重要です。
反射する素材でできたものや、ホログラム加工されたものがおすすめ。
「きゃっ、まぶしい!」とアライグマも目を細めちゃうかも。
設置場所は、風通しの良い場所を選びましょう。
農地の四隅や、アライグマが侵入しそうな場所が狙い目です。
「よいしょ」と、しっかり地面に刺して。
高さも大切なポイント。
地面から1〜1.5メートルくらいの高さが効果的です。
アライグマの目線に入りやすい高さなんですよ。
複数の風車を設置する場合は、不規則な配置がおすすめ。
「あっちにもこっちにも、どこを向いても風車だらけ!」とアライグマを混乱させられます。
ただし、注意点もあります。
強風の日は風車が飛ばされないよう、しっかり固定しましょう。
「あらら、風車が空を飛んでる!」なんてことにならないように気をつけてくださいね。
また、定期的なメンテナンスも忘れずに。
埃や汚れが付くと反射効果が落ちてしまうので、時々拭き掃除をしましょう。
「ピカピカ、ピッカピカ」と磨いて、いつでも最高の効果を発揮できるようにしておくんです。
風車以外にも、動くものを利用した対策を活用することもできます。
例えば、風に揺れるキラキラテープや、ゆらゆら動くペットボトルの風鈴なんかも効果的。
「キラキラ、ゆらゆら、ちゃりんちゃりん」と、アライグマを驚かせる仕掛けをあちこちに設置してみましょう。
この「動く風車」作戦、見た目も楽しいアライグマ対策です。
農地を守りながら、ちょっとしたアート作品のような雰囲気も楽しめちゃいます。
「よーし、今日から我が農地はアライグマ撃退アートギャラリーだ!」なんて気分で、楽しみながら対策を進めてみてはいかがでしょうか。